ビジネス会計検定(2級)受験メモ
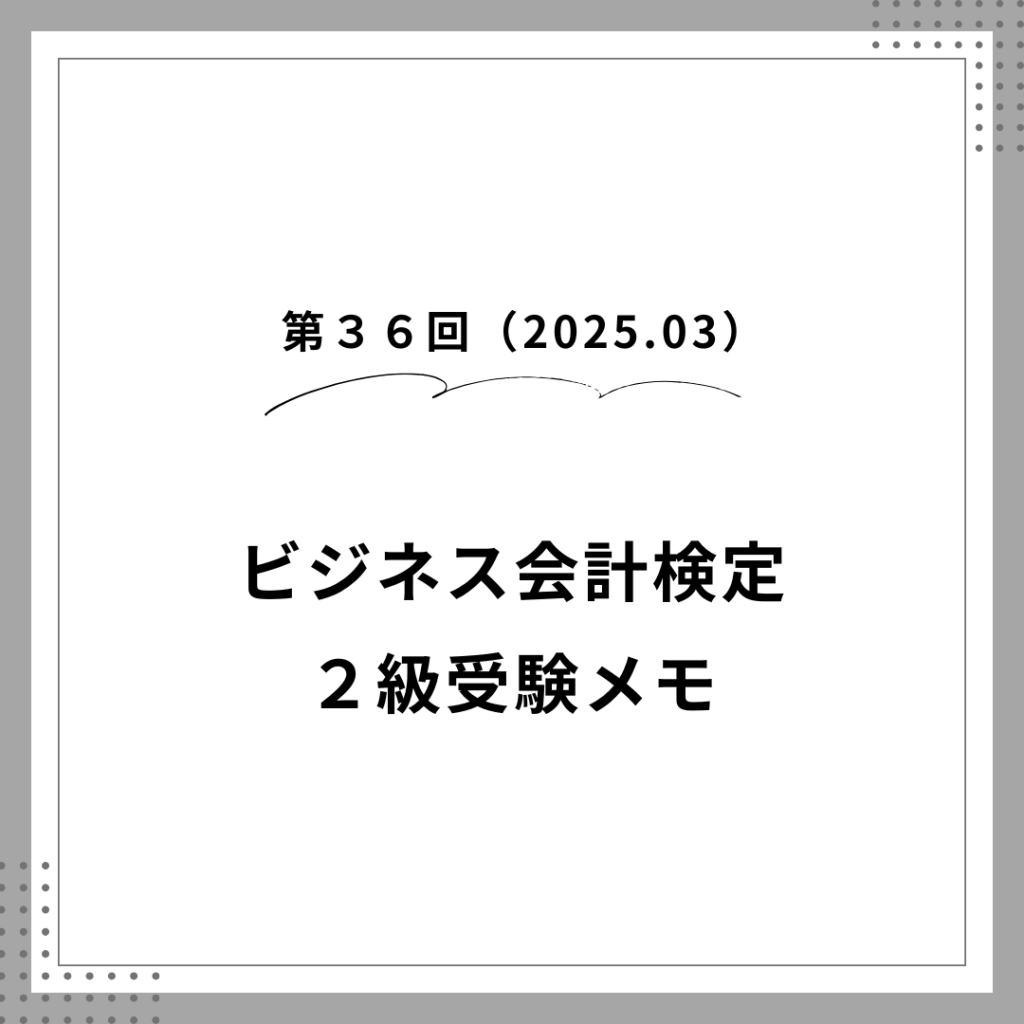
試験概要・当日の流れ
大阪商工会議所主催のビジネス会計検定を受験しました。
3級、2級、1級とあるうちの2級を選択。
簿記とのすみわけは経理処理を行う側とそれを活用する側、という重点領域の違いのようです。
どちらが易しい、難しい、というよりは棲み分けがあると思います。(世間的な認知度は圧倒的に簿記の方が高いでしょうね。)
最近はCBT形式が主流になってきているのか、会場型の試験は久しぶりでした。
初めて降りる駅でしたが、そういえば少し前のあいみょんの歌の歌詞に出てきていたような…?、という記憶は当日調べたところ合っていたようです。
時間拘束はネックですが、行ったことのない大学のキャンパスを見られたりするのはたまには面白いですね。(昨今の事情からかあまり自由に歩き回れる雰囲気ではありませんでしたが。)
2級は午前開始で、1級・3級は午後開始。(1級または3級と併願可能にするためこうなっているようです。)
受験票(ハガキ)記載の10時集合はあくまで集合で、開始は試験説明後でした。
結果
自己採点結果 80点 (70点合格)
第1問 16/18 第2問 22/32 第3問 42/50
後半時間がなくなってからも、問題用紙にメモはしていたので、マークミスがない限りは上記の通りかと思います。
感想
今回からなのか、前回もそうだったのかは不明ですが、公式問題集に収録されている第34回以前と違って、大問3が大問4と統合されて2社比較と2年度比較が織り交ぜられる形式になっていました。(この形式については公開されている解答速報から推察すると昨年10月もそうだった様子ですが。)
従来の過去問だと、各指数の計算は多少スピードを落としても細かく、検算しながら取り組んだ方が高得点を狙える印象でしたが、今回の形式でそれをやると(少なくとも過去問で当落線上の実力では)明らかに時間不足な調整でした。実際、大問2が終わった段階では、120分の時間のうち70分強は残っていたので、大問3に着手した段階では、時間は十分かな、と思っていました。ところが解き進めてみると、かなり計算ボリュームのある問題も多く、半分くらい終わった段階で残り30分を切っていて、精度を落とすことに決めました。数字の開きがあるものは、増減や大小だけ見て回答に関係しなさそうな計算は省く、計算式を書かない&検算しない、という割り切りでどうにか時間ギリギリ。
ただ、1問ごとに見ていくと、個別の問題の難易度はそう変わっていなさそう(どちらかというと、細かい数値の違いが正答に影響しないものが増えて易化)で、スタイルの変更みたいですね。
方向性はわからなくもないですが、スピードを重視するのであれば、CBTに移行してExcelを使わせて欲しいところではありますね。(今時実務で電卓と手書きということはないでしょうし。)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。






この記事へのコメントはありません。